AIが文章を書き、画像を作り、医療を助けるようになった今、
「AIが裁判に関わる日」も現実味を帯びている。
すでに海外では、AIが判決の補助や判例検索に使われ始めている。
しかし、AIは“人の罪”を理解できるのか?
「公正」「感情」「赦し」──これら人間的な判断を、
機械がどこまで担えるのかを考えることは、
近年、エストニアや中国では「AI裁判官」が導入されている。
AIが過去の膨大な判例データを参照し、似たケースの判決を提示する仕組みだ。
これは「司法の効率化」という点では非常に優秀で、
人間の裁判官が見落としがちな要素を補うこともできる(これだけで天職)
ただし、それは“判例の平均値”に基づいた判断。
AIは「前例にない事例」に弱く、個別の事情や感情を汲み取ることができない。
司法の本質である「人間の苦悩」や「再犯への希望」など、
定量化できない価値を扱うことが難しい。
AIは偏見を持たず、感情にも左右されません。
しかしその“公正さ”は、逆に“冷酷さ”と表裏一体です。
AIが判断を下すとき、そこに「赦し」や「共感」がない(国によっては感情や温情で裁量が決まる事もある為、マイナス)
たとえば、貧困・病気・家庭環境などの背景を考慮するのは人間の倫理判断。
AIがそれを「データ外のノイズ」として切り捨ててしまえば、
“平等”ではあっても“公正”ではない結果が生まれる。
哲学者アリストテレスが説いた「正義」とは、
単なるルール適用ではなく、“状況に応じた配慮”である。
AIにはこの柔軟さがなく、“完璧な不完全さ”を持つのが人間の裁きだと思う。
理想は、AIが“客観的補助”を行い、
最終的な判断は“人間の倫理”が下すハイブリッドな司法だと思う。
AIは膨大な情報を整理し、偏りをチェックする役割に。
一方で、人間は情状酌量や更生の意志など“人間らしさ”を担当したらどうだろうか。
AIが司法に関わることは、「人間の判断を置き換える」ことではなく、
「より正確に支える」こと、なのかも。
そのバランスを保つことが、これからの社会の大きな課題になる。
AIは法律を理解できても、罪を“感じる”ことはできない。
だからこそ、AIを司法に導入する際に問われるのは、
技術ではなく“倫理”だ。
人間の判断を完全に排除するのではなく、
AIと共に「より公正で、より人間的な裁判」を目指すこと。

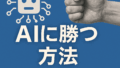

コメント